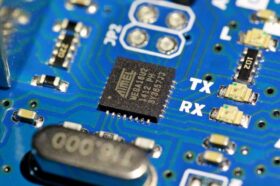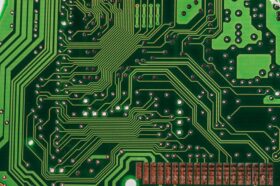日曜大工から引っ越し、大掃除、畑作業、草むしりなど多くの場所で活躍する軍手。幼い頃から現在に至るまで何度か着用した経験があるのではないでしょうか?
この軍手、いつ頃から、どんな目的で使われているかご存じですか?そして今なお廃れずに、多くの用途に使用されているのは、なぜなのでしょうか?
今回は、工場の仕事でもおなじみの軍手についてご紹介します。
いつどこで使うの? いろいろある軍手の種類
一見どれも同じに見える軍手ですが、実は糸の材質などによっていくつかの種類に分かれます。軍手の主な種類について説明します。
純綿軍手
綿100%の天然繊維で編み上げた軍手です。ほかの種類と比較しても丈夫で、火に強いのが特徴です。色はかすかに黄色、またはグレーがかっていて、着けたときに少しごわつきます。汗をよく吸うので、特に夏場の作業に向いています。
特紡軍手
主にポリエステルなどの合成繊維を紡績し直した糸で作られています。耐久性が低く、高熱の物に触れると溶けます。しかし、値段が安いため、一般的に幅広く使われています。色は白です。
混紡軍手
綿、ポリエステル、レーヨンなどの繊維を混ぜ合わせた糸で編まれた軍手です。特紡軍手と比較すると綿の混合率が高いため、柔らかくて耐久性が高くなっています。色は少し茶色がかっています。
日本が発祥! 軍手の歴史とは?
軍手は日本発祥で、もともとは「軍用手袋」を略したものです。軍手が最初に登場したのは江戸時代末期の長州藩、現在の山口県のあたりでした。鉄砲を使った武装訓練のときに、素手で鉄砲に触ると錆びやすいので、それを防ぐために使用されたのが始まりとされています。その後、徳川幕府がつくった軍隊や、明治に入ってから結成された軍隊内で需要が高まりました。その頃から「軍用手袋」、略して「軍手」と呼ばれるようになりました。当時は作業用としてだけでなく、防寒具として着用されることが多かったようです。
第2次世界大戦直後までは高価なものでしたが、終戦後の1950年代に半自動機織り機が開発されたのをきっかけに、指の部分が簡単に縫えたり、手首の部分にゴム糸を通すことができるようになり、安価で安全性の高い軍手が登場しました。さらに1960年代には世界初の全自動手袋編み機が開発され、生産量が急激に増加しました。こうして「軍人の手袋」であった軍手は、現在のような「大掃除には欠かせない作業用手袋」へと変わっていったのです。
こんなものも! ちょっと変わった軍手いろいろ
最後に、変わり種の軍手を紹介します。
スマホ用軍手
普通、スマートフォンのタッチパネルに軍手をしたまま触れても反応しません。タッチパネルの表面はわずかな静電気で覆われていて、指で触れると静電気が指に吸い取られます。どの部分の静電気が吸い取られたかをスマホが読み取って、指が触れた場所を特定し操作が行われるのです。軍手などの手袋を装着していると、タッチパネルに認識されないのですが、スマホ用軍手の場合は指先に「高感度導電糸」が縫い込まれているため、軍手をつけたままタッチパネルの操作ができます。スマホだけでなく、工場で使用する機器類のタッチパネルでも同じように使えます。いちいち軍手を外さなくていいなんて、これは便利ですね。
スマホケース
世の中にはたくさんのスマホケースが存在しますが、なんと軍手もスマホケースにエントリーしていました。軍手の中にスマートフォンがすっぽり入り、しかも手首部分を巾着袋のようにヒモで締めることができます。しかもこの軍手、ではなくスマホケース、軍手づくり50年以上という大ベテラン職人さんの作品です。乱れのない非常に美しい編み目や指先のつくりなどが、職人の本気を感じさせます。
肉球がついた軍手
軍手の中には、手のひら部分一面に滑り止めのついたものがあります。なかには、手のひら一面に猫の肉球のついた軍手もあります。お遊び商品ではありません。「猫」のマークで有名な運送会社で実際に使用されている軍手で、「社員たちに、会社や仕事に対して愛情や親しみを感じてほしい」という思いから誕生したのだとか。ブルー、グリーン、ピンクと3種類のカラーリングがあり、好みの色を選ぶことができます。とてもユニークでかわいい肉球軍手。あくまで社員用とのことですが、ネットなどで購入することができます。
いくつもの戦乱を乗り越えてきた軍手の未来とは?
普段何気なく使っている軍手ですが、その名の通り、もともとは軍隊で使用されていたものでした。いくつもの戦争を経て現代に伝わり、それが形を変えながらも、今なお幅広く使用されているというのは驚きです。それだけ使いやすく、品質も良いということでしょう。種類というと、以前は「カラー軍手」程度でしたが、現在では軍手をしたままスマホのタッチパネルを操作できるものなど、便利なものが登場しています。これから先、どんな軍手が現れるのでしょうか?軍手の歴史、まだまだ続きそうです。
制作:工場タイムズ編集部