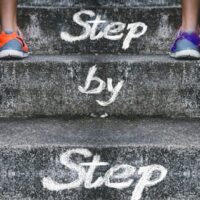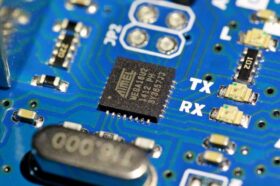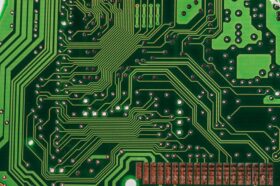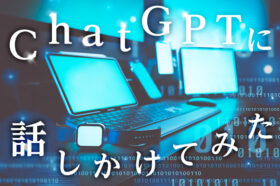テレビやパソコンなどを購入すると、必ず「マニュアル」が付いていますよね。
マニュアルは正しい使い方を覚えることで、製品を安心して楽しむためのものです。また、どんな仕事にも、業務を正しく行うためのマニュアルが存在します。
今回は工場の仕事で使われるマニュアルについてご紹介します。
なぜマニュアルは必要なのか?
そもそも工場の仕事にマニュアルが必要なのはなぜでしょうか?それには理由があります。
作業を標準化できる
一番大きな理由は作業の標準化です。作業の標準化とは、いつ・誰が作業を行っても同じ品質の製品をつくれるようにすることです。工場の仕事はひとりで行うわけではありません。たとえば同じ部品を取り付ける作業でも、作業をする人は交代します。そのたびに部品の取り付け方が変わっていては大変なことになりますよね。そうならないようにするためにマニュアルが存在するのです。
教育期間を短縮できる
職場に新しい人が入ったとき、ひと通りの仕事ができるようになるまでは研修が必要です。そんなときにマニュアルがあれば、基本的な作業内容については先輩の手を借りることなく自分で覚えることができます。逆にマニュアルがなければ、すべてをはじめから教わることになり、手間も時間もかかります。新人が仕事を覚えるまでの時間を短くできます。
「作業の見える化」ができる
マニュアルがないとそれぞれの人たちがいまどんな作業をしているのか、あやふやな状態になりがちです。マニュアル通りの作業手順に従うことによって何かトラブルが起きたときにも、周囲の人にすぐ作業状態を共有できるのでスムーズな対応をとることができます。
「作業の振り返り」に使える
ミスしたときやうまくいかないとき、マニュアルがあればどこを改善すればいいのか全体の流れを振り返って確認することができます。マニュアルがあれば先輩や上司に見てもらうことなく、自分の作業をひとりで調整することもできるでしょう。
このようにマニュアルがあると、作業が速く、スムーズに運びます。またマニュアルをつくることで作業における無駄を減らすことができ、生産の効率化につながります。
工場内でのマニュアルの作り方とは?
マニュアルとは仕事の説明書のようなものです。では、工場でのマニュアルはどのようにしてつくられているのでしょうか。
マニュアルをつくるには、まず工場での作業をすべて洗い出します。たとえばお菓子をつくっている食品メーカーの場合を考えてみましょう。小麦粉や野菜などの材料を運んで機械に入れ、揚げたり焼いたりして製品をつくります。そのうえで不良品のチェックを行い、合格した製品を袋に詰めて出荷します。全体でどんな作業があるのか徹底的に洗い出してみることがマニュアルづくりをはじめるにあたっての第一歩です。
多くのマニュアルは「仕事の目的」「仕事の流れ」「作業の手順」「製品の品質水準」「チェックリスト」などの項目で構成されています。マニュアルの記載は、「なぜそのお菓子をつくるのか、どんな特徴があるのか」を書くことからはじまります。そこからお菓子ができるまでの全工程を説明していき、仕事の全体像がわかるようにします。
そのうえで製品の種類ごとにどんな材料を使うのかという説明や、お菓子をつくる機械の動かし方など具体的な手順を解説していきます。ほかには会社が求める製品の品質や作業時間の目安を示し、作業の習得や振り返りに使えるチェックリストを加えていきます。
マニュアルをつくるときのポイントは「わかりやすさ」です。特に作業手順については、初心者が簡単に理解できるよう写真や図を使ってひと目でわかるようにしたいところです。「良い例」と「悪い例」を同時に示すことができれば、より覚えやすいでしょう。
また、基本的な手順と作業のコツを分けて書いておくと、うまくいかない作業があるとき従業員はマニュアルを見て作業を改善しやすくなるでしょう。注意点や専門用語については説明が長くなることがあるので、別に「チェックリスト」や「用語集」をつくる場合があります。
マニュアルを活かすためには?
現場にマニュアルを浸透させるためには、どのような点に気を付ければいいのでしょうか。
実践練習
ひと通りマニュアルをつくったら、完成前に現場で実際に使ってみましょう。考えている段階では見えなかったことが実践を繰り返すことによって、よく見えてきます。
「報・連・相」を習慣化する
仕事をするうえでの基本中の基本が「報告」「連絡」「相談」という、いわゆる「ホウレンソウ」です。マニュアルを活かすためにこの3つは欠かせません。マニュアルのとおりに実行したら責任者や上司に報告し、各部署の担当者と連絡を取り合って情報を共有する。わからない点や問題点があれば相談するといったことが大切です。
必要に合わせてマニュアルを改善する
マニュアル通りに実践しても、うまくいかない場合はマニュアルの記載を改善します。現場で働く人たちの意見を積極的に取り入れみんなでマニュアルを作り上げていきましょう。そうすれば従業員全体の理解が上がって生産性を高めることができます。
PDCAを速く回す
「PDCA」というのはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のことです。これはもともと生産管理や品質管理を効率よく行うために考え出されたものです。マニュアルをつくったら現場で実践し、うまくできているかを評価する。問題点があれば改善するという流れです。PDCAを速く回して改善すれば、生産性をより高めることができます。
働く人たちの自主性を育てる
より良い工場にするためには、作業をする人の自主性を育てることが大切です。マニュアル通りに作業をしているだけでは、作業を「やらされている」と感じてしまいます。これでは作業をする人たちのモチベーションは上がりにくく、高い生産性は望めません。目標や目的をはっきりさせるためにもマニュアルを活用するようにしましょう。
マニュアルと一緒に進歩を
マニュアルは現場で働く人たちにとって、自分たちの仕事を効率化できるアイテムです。社員全体で価値観を共有し、高い品質の製品をつくり続けていけば会社も社員も成長を続けられます。現在のマニュアルを見直すだけでも、作業の改善を行うことができるかもしれません。
制作:工場タイムズ編集部