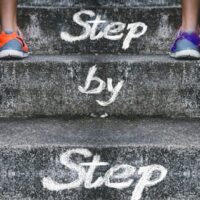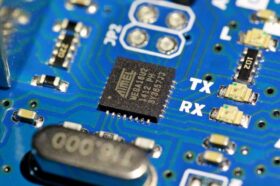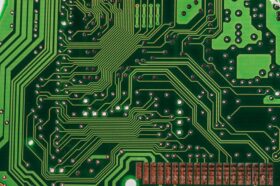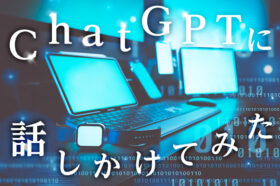いつも身近にあり値段も安いボールペン。
書き味はなめらかで、くっきり明瞭で読みやすい。ところが一度書いたら消せません。カレンダーの余白にちょっと予定を書き込む。でも予定は未定。15日の約束が17日にずれる、なんてことはよくあります。文字の上に二重線でも引いて、その下に書き直したりしますが、これがかなり目ざわり。シャープペンシルのように簡単に消せる手軽さはありません。でもこんな常識は過去の話。いまは、「消せるボールペン」があります。その便利さから個人用途はもちろん会社の常備品としても使われるようになっています。
では、どうして「消せる」のか。その仕組みを紹介します。
インクが消える!? その仕組みとは?
消せるボールペンの秘密は、そのインクにあります。「フリクション(摩擦)インク」と呼ばれていて、インクの中に直径2~3ミクロンにまで小さくしたマイクロカプセルが含まれています。このカプセルの中に「発色剤」(「赤」や「黒」などの色を決める成分)、「顕色剤」(発色させる成分)、「変色温度調整剤」の3つの成分が入っています。
変色温度調整剤というのがキモで、常温ならばカプセルの中の発色剤と顕色剤が結びついて文字が書けます。その文字の上をボールペンのキャップに付いているラバーでこすると摩擦熱が発生(摂氏60度以上になります)します。ここで変色温度調整剤が働き、発色剤と顕色剤が離ればなれになって色が消えるというわけです。一度消えた文字はそのままの状態を保ちます。つまり、メモリー機能を持っているわけです。ただし、インク自体がなくなったわけではありません。マイナス20度まで冷やすと消した文字が再び現れてきます。
便利な消えるインク! メリットとデメリット
消えるインクで書いたものは、ほかの油性、水性などのボールペンと同じで、長期にわたり保存できます。ただし、温度に反応する仕組みが長所とも短所ともなります。
消えるインクのメリット
ビジネスシーンでもよく使われるボールペン。社内で回覧する歓迎会のお知らせを書いていて、1字だけのミスで全文書き直しでは疲れます。修正液を使えば、その跡が残ってみっともない。ビジネスの場ではきれいな文書をつくるのも実力のうちです。こんなときに消せるボールペンは重宝します。システム手帳で使うとさらに便利です。取り消し線だらけだったスケジュールが見やすくスッキリします。消去用のラバーは専用に開発されたもので、消しゴムのようなカスは出ませんし、摩耗しにくく繰り返して使えます。消した跡は鉛筆やシャープペンシルよりきれいなうえ、何度でも書き直せます。
消えるインクのデメリット
せっかく書き上げた書類も、ドライヤーの熱にあてたり、真夏の車内に放置したりすると、跡形もなく文字は消えてしまいます。気温が40度になれば道路のアルファルト面は65度に達するといいます。そんなところに、うっかり書類を落としたりすると、せっかく書いた文字が消えてしまい、悲劇です。郵便物の宛名書きに消せるボールペンを使うのも考えものです。郵便物が相手先に届くまでにどんな環境に置かれるか、予想がつきません。また、消せるボールペンは公的書類に使わないようメーカーも注意しています。これはデメリットの一つと考えてもいいと思いますが、履歴書や請求書、領収書などには使えません。実際に悪用する人もいて、虚偽有印公文書作成の疑いで書類送検された例もあります。このごろは大学の入学願書でも、「消せるボールペンの使用禁止」の注意書きがみられます。
まだある! 色が変わる技術の利用法
消せるインクの元になった技術は1972年に日本の筆記具メーカーが開発しました。その当時はボールペンに応用するという考えはありませんでした。ボールペン用のインクとしては、設定温度の幅が狭かったり、ごく小さなマイクロカプセルをつくる技術がなかったからです。そこで76年にまず登場したのが「魔法のコップ」でした。これは紙コップに冷えた飲み物を注ぐと隠れていた絵が浮き出てきます。
反対に、熱い湯を入れると絵が現れるマグカップも発売されました。85年にはおもちゃ市場に進出、「お化粧遊び人形」が売り出されました。人形の顔を冷たい水でなでるとアイシャドーや口紅、頬紅が浮かび上がり、お湯でこすると元にもどります。設定した温度になるとインクの色が変わる性質から、ビールやワインのおいしい飲み頃を教えてくれるラベルにも応用されました。
一方、人に渡した書き物が、いつでもきれいに消せるのでは落ち着かないという人もいます。そこで、書いているときは消しゴムで消せても、1日たつと消せなくなるというボールペンもあります。これは海外製で、フリクションインクとは違って特殊な油性インクを使っています。
35年をかけて生まれた、息の長いヒット商品
消せるボールペンは筆記具メーカーにとっては狙い目の商品でした。ニーズは強いという確信もありました。ところが1980年代に商品化されたものの、やがて姿を消しました。消しゴムを使って文字は消せるのですが、いつでも簡単にきれいに、とはいかなかったからです。欠点を克服して、2007年に登場したのがフリクションインクを使ったボールペンでした。
1年や2年の短い期間で生まれてきた商品ではありません。原理の発見から商品化まで、およそ35年にわたる試行錯誤が続けられています。着想し、原理を確かめ、改良し、応用については海外メーカーとの共同開発なども経て、ついにボールペンのインクとして実用に耐えるまでのレベルにいたりました。フリクションインクを使ったボールペンの販売本数はいまやシリーズ累計で10億本を超えるヒット商品になっています。一度試してみる価値はありそうです。
制作:工場タイムズ編集部