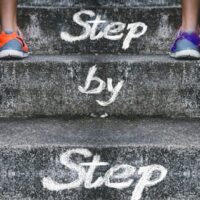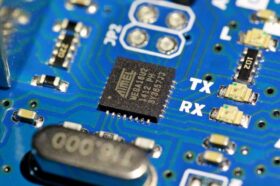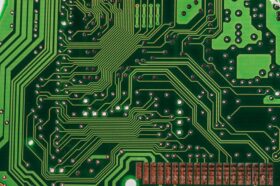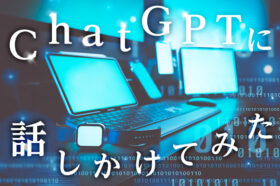日本人の食生活に欠かせないのが醤油(しょうゆ)です。卓上調味料として、煮炊きに使う調理用として、毎日の食卓で幅広く使われています。
しかし、これだけ身近な商品なのに、醤油の歴史や製造工程まで知っている人は、それほど多くないかもしれません。
今回は、日本人の食卓を支える醤油の魅力と、醤油が醤油工場でどのように作られているかについてご紹介します。
日本の食文化に欠かせない醤油
醤油はどのようにして誕生し、その歴史の中でどんな種類に分けられていったのでしょうか?まずは醤油の歴史と種類、そして健康効果についてお伝えします。
醤油の歴史
醤油のルーツは、古代中国で誕生した塩漬けの発酵食品である「醤(ひしお)」だと言われています。日本には縄文時代にすでに醤があったという説が有力です。醤の中には野菜・果実・海藻などを材料とした「草醤(くさびしお)」、魚を材料とした「魚醤(うおびしお)」、穀物を材料とした「穀醤(こくびしお)」などがあり、今でいう味噌と醤油を合わせたような食品だったようです。鎌倉時代には中国から金山寺(きんざんじ)味噌という味噌の製法が伝わったのですが、その製法を村民たちに伝えていた覚心(かくしん)というお坊さんが味噌から染み出した液体のおいしさに気付き、その液体を煮炊きに使うようになったのが「たまり醤油」のはじまりといわれています。
日本の文献では、室町時代に刊行された『易林本 節用集』(えきりんぼん せつようしゅう)の中に初めて醤油に触れたくだりが出てきます。その後、江戸時代には醤油が全国で生産されるようになり、現在では「ソイソース」として海外へ輸出されるまでに発展しました。
醤油の種類
醤油にはいろいろな分類方法があり、JAS(日本農林規格)では「種類」「製法」「等級」の3つの方法で醤油を分けています。
【種類による分類】醤油を種類で分類すると、「濃口(こいくち)」「淡口(うすくち)」「溜(たまり)」「再仕込み」「白(しろ)」の5種類となります。
濃口醤油
全国の生産量の8割以上を占めている醤油です。原料は大豆と小麦をほぼ同量ずつ使用します。味わいと香りのバランスが良く、卓上調味料、調理用として幅広く使われています。
淡口醤油
色が淡いことから名前に「うすくち」と入っているのですが、塩分は濃口しょうゆよりも高くなっています。香りやうま味が控えめなため、素材の味や色合いを活かしたい料理に向いています。
溜醤油
ほぼ大豆のみから作られている醤油で、大豆由来の旨み成分が豊富に含まれているため、濃厚な味わいが楽しめます。刺身のつけ醤油や、せんべい、佃煮などに使用されます。
再仕込み醤油
食塩水の代わりにできたばかりの「生の醤油」を使って再び醤油を仕込む製法を用いるため、再仕込み醤油と呼ばれています。色が濃く風味も濃厚で、主に刺し身や寿司のつけ醤油として使われています。
白醤油
小麦を主原料にして、少量の炒った大豆を加えて麹をつくる醤油です。小麦由来の豊かな香りを活かして低温・短時間で発酵させているため、穏やかな味わいに仕上がっています。糖分が高いのも特徴で、うどんのつゆや高級料理の隠し味として用いられています。
【製法による分類】醤油の製造方式には「本醸造」「混合醸造」「混合」の3種類があります。
本醸造方式
原料となる大豆・小麦を麹菌や酵母などによって発酵・熟成させて作ります。現在では全体の8割が本醸造方式で作られています。
混合醸造方式
本醸造の「もろみ」(醤油麹に食塩水を混ぜ合わせた、発酵前の醤油の元になるもの)にアミノ酸液を加え、短期間熟成させる製法です。
混合方式
もろみを圧搾しただけの火入れ前の状態の「生揚げ(きあげ)醤油」に、アミノ酸液を直接混ぜ合わせて醤油を作る製法です。
【等級による分類】醤油にも等級があり、醤油の旨みの指標とされているグルタミン酸などの窒素分の含有量や色の濃淡により「特級」「上級」「標準」に区分されます。さらに特級よりも窒素分が10%以上多いものは「特選」、20%以上多いものは「超特選」と表示することができます。
醤油の効能
健康面ではあまり注目されてきませんでしたが、実は醤油には多くの優れた効能があり、摂取することで消臭、殺菌、抗酸化によるガン予防、さらにはアレルギー症状の改善にも役立つと言われています。これは醤油に含まれるアミノ酸類や、発酵・熟成の過程で生まれる成分の働きによるものです。塩分を多く含むので、過剰摂取すると高血圧の原因になってしまいますが、適度な量を口にすることで健康な体を保つ助けとなってくれるのです。
醤油工場での製造工程を教えて!
醤油は、大豆・小麦・食塩の3つの原料から作られます。醤油工場で行われている製造工程についてお伝えします。
麹づくり
まず、蒸した大豆と炒った小麦を混ぜたものに麹菌を加え、麹のもとを作ります。昔は自然界に生息している麹菌がついて麹ができるのを待っていましたが、現在は培養して保管してある麹菌を使用するのが一般的です。この麹のもとは、温度・湿度を管理しながら3日ほどかけて麹菌を育成させ、醤油麹となります。
仕込み・発酵
次に出来上がった醤油麹に食塩水を混ぜた「もろみ」を発酵・熟成させていきます。大豆のタンパク質と小麦のデンプンが酵素や乳酸菌、酵母の働きによって分解されて、醤油独特のおいしさや香り、色を作り出していきます。
熟成・圧搾
数カ月から1年半の期間をかけて発酵させて、微生物の活動が落ち着いてくると、もろみは調和のとれた状態に熟成されていきます。仕上がったもろみは布に包まれ、初めはゆっくりと、それから徐々に圧をかけながら圧搾していきます。
火入れ
こうして絞られた醤油(生揚げ醤油)を80~85℃の温度で10~30分ほど加熱していきます。この火入れをすることで微生物が殺菌され、色沢が整えられ、香ばしい香りがつきます。
最後に品質検査に合格した醤油だけが醤油工場から出荷され、私たちの手元へと届けられます。
え、そこに!? 醤油の意外な使われ方
紀元前の昔から作られている醤油ですが、現在も進化し続け、バリエーション豊かな醤油が作られています。ちょっとマニアックな!?醤油事情についてご紹介します。
専用醤油
醤油はいろいろな素材にマッチする万能調味料ですが、あえて「◯◯専用醤油」というものもあります。たとえば「ライス専用醤油」は、ご飯にかけて食べるためだけに開発された、やや甘めの醤油です。白米を単体で食べる文化にあまり馴染みがない、海外向けに販売されています。また、「プリン醤油」は、「プリンに醤油をかけるとウニの味がする」という都市伝説を再現したもので、ベンチャー企業と老舗醤油店の共同開発で作られ、メディアにも取り上げられました。企画第2弾として発売された「かき氷専用醤油」も大ヒットしています。
燻製醤油
こちらは、燻製にかけた鰹節を醤油に漬け込んでスモークの香りを移した商品で、普通の醤油のように使うと、かけた食材がスモーク風味になるという斬新な醤油です。チーズやサーモンをつけて食べるほか、ゆで卵にたらして燻製卵にしたり、手作りパンに少し加えて燻製醤油バゲットを作ったりと、アイデア次第でいろいろな楽しみ方ができます。
ほかにも、醤油にダシやホタテ、牡蠣(かき)などのエキス分を加えて旨みを増した「ダシ醤油」も多くのメーカーから発売されています。これからもさらにバリエーション豊かな醤油が登場することでしょう。
日本の食卓を支える醤油工場の役割
毎日のように利用している醤油ですが、商品として出来上がるまでにはたくさんの人が関わり、厳しい品質チェックを経てようやく私たちの手元へ届けられています。醤油は日本料理の基本とも言える調味料です。その醤油は醤油工場で作られています。今回は醤油の歴史や種類、製造工程をお伝えしましたが、醤油に興味が湧いてきた人は、醤油工場の見学や醤油づくりのワークショップに出掛けてみてはどうでしょうか?さらに興味が出てくるかもしれませんよ。
制作:工場タイムズ編集部