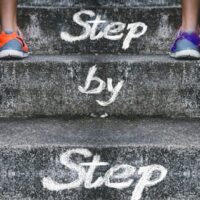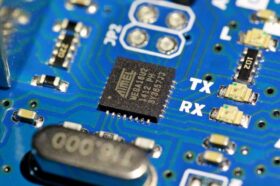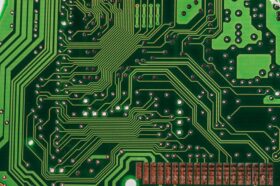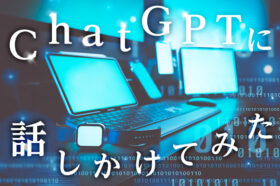漆器とは、木や竹などに漆(うるし)の木からとり出した樹液を塗り重ねていく、日本の伝統工芸品です。
熱や酸などの刺激に強いため、長持ちするというメリットに加え、贈答品や文化財としても使われるなど、見た目の美しさも魅力です。高級品になると、手作りが一般的ですが、近年は工場で大量生産された製品をスーパーなどで見掛けます。
今回は漆器の製造方法や漆器製造の仕事についてご紹介します。
漆器のことを詳しく教えて!
まずは、知っているようで案外知らないことが多い漆器の基礎知識についてお伝えします。
漆器とは
漆の木から採れる樹液のことを生漆(きうるし)、それをろ過し煮詰めたものを漆液(うるしえき)といいます。漆液を木や竹、皮などの素材に何度も塗り重ね、器物として仕上げたモノが漆器です。
有名な漆器
一口に漆器と言っても、使用した素材や用途によっていろいろな種類に分けられます。お茶碗やお皿などの家庭で使う生活用品のほか、芸術品として扱われる高級品もあり、贈り物として人気があります。
有名な漆器には、「輪島塗」や「若狭塗」などがあります。優れた漆器は、完成までに漆液を何度も塗り重ね、時間をかけてていねいにつくられます。輪島塗の中には、完成までに30回以上の塗り作業を行うものもあります。一方、若狭塗は、貝殻模様や卵殻模様といった特徴的なデザインで知られます。特に塗箸(ぬりはし)が有名で、米国のバラク・オバマ大統領にも、若狭塗の箸が贈られました。
漆器の価格帯
100円均一で買える安いものから、数万円する高価なものまで価格にも幅があります。これは、大量生産か手作業かといった製造方法の違いや、漆の材料費の違いなどが影響しています。
漆器って、どうやって作るの?
ひとつの漆器が生まれるまでには、多くの手間と長い時間が必要です。続いては漆器作りの工程についてお伝えします。
木地(きじ)作り
「お茶碗なら丸物」「重箱であれば板物」といった具合に木地の形が違うため、漆器作りはそれぞれに適した木地を作ることからはじまります。たとえば丸物なら基本の形を作ってから最低2週間かけて水分を抜き、ろくろの作業を行います。板物であれば箱の形を作ってから必要に応じて「のこぎりで挽き曲げを仕込む」「湯曲げで丸みをつける」といった作業を行います。
下地(したじ)付け
下地付けの中にも渋下地(しぶしたじ)と錆下地(さびしたじ)の2種類があります。渋下地は豆柿の渋に油煙(ゆえん)、または炭粉(すみこ)や松煙(まつほこり)などを混ぜ合わせたものを塗り付けて、繰り返し研ぎを行った後で柿渋を塗るというものです。錆下地は生漆に砥之粉(とのこ=砥石を切り出したときに出る粉末)を混ぜ合わせたものを塗り付けます。
塗り(ぬり)
塗りの工程には「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3段階があります。一度塗っては乾燥させ、研ぐという流れを何度も繰り返し、最後に上塗りを行います。
加飾(かしょく)
筆に金粉や銀粉などをつけ、漆器に美しい絵柄や模様を描く仕上げの工程です。絵を彫ってから金箔や顔料などを使用して描く「沈金」(ちんきん)という方法もあります。現在では「スクリーン印刷」という方法もあり、こちらは少ない手間でたくさんの加飾を施すことが可能です。
漆器製造工になるには?
最後に、漆器製造を仕事とする「漆器製造工」になるための方法についてご紹介します。
漆器製造工の仕事内容
漆器は完成するまでに30以上もの工程を踏むことになります。伝統工芸品としてひとつの漆器に時間をかけて制作するのか、それとも家庭用として一度にたくさんの数を作るのか。漆器を制作する工房の方針によって仕事内容は変わってきます。
漆器製造工になる方法
特別な資格はなくても漆器製造工になれます。漆器製造工は昔から存在する職業であるため、現役で活躍する漆器製造工に弟子入りをし、技術を学ぶという制度が今も残っています。それ以外には、専門学校や職業訓練校で漆器製造について学び、そこから弟子入りして経験を積む方法もあります。
漆器製造工のやりがい
漆器製造工は、クオリティの高い漆器を完成させるために、相当な手間と時間をかけています。しかも漆器は世界に誇る芸術品です。丹精を込めて一つの漆器を完成させたときの喜びは大きく、やりがいを感じられるでしょう。
世界に誇る漆器を自分の手で生み出す喜び
漆器は産地や用途によって工程や材料が変わりますが、いずれも昔ながらの技術を受け継いできた「文化の結晶」と呼べるものです。漆器、または伝統工芸品の制作というモノづくりに興味がある人は、漆器製造工の仕事について考えてみるのもいいでしょう。まずは、漆器製造工の育成に力を入れている産地をネットなどで調べてみてはいかがでしょうか?
制作:工場タイムズ編集部