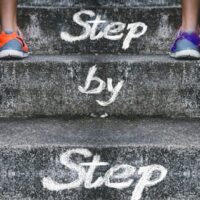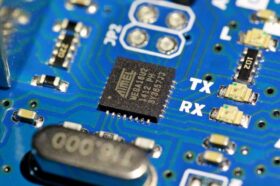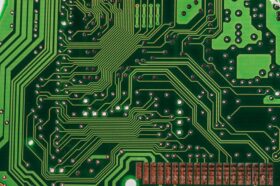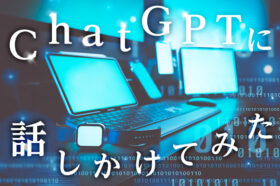2015年にドイツで開かれた第39回世界遺産委員会で、新たに世界中の文化的、歴史的価値を持つ遺産として計24件が世界遺産に登録されました。
日本からは「明治日本の産業革命遺産」が選ばれたことで話題になりましたね。日本の物件の中で特にメディアに取り上げられ注目されたのは長崎県の「端島(はしま。通称:軍艦島)」ですが、ほかにも注目の遺跡や施設があります。
その中で今回は、造船に関する施設を中心にご紹介します。
明治日本の産業革命遺産
「明治日本の産業革命遺産」は、2007年の「石見(いわみ)銀山遺跡とその文化的景観」、2014年の「富岡製糸場と絹(きぬ)産業遺産群」に続くものです。正式名称は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製銅、造船、石炭産業」で、明治の重産業発展に貢献した物件をまとめ、8エリア、23の資産が登録されています。
この世界遺産登録によって、一躍注目されるようになったのが軍艦島です。石炭の炭鉱として1886年からおよそ100年近く、日本の石炭算出の主要地でした。外見が軍艦のように見えたこと、日本で初めてコンクリート製の集合住宅が建てられたことなどに話題が集まり、映画のロケ地としても利用されています。
長崎造船所
明治維新の際に、もっとも外国との交流が盛んだった地域の一つに長崎県があります。もともと出島(江戸幕府がつくった人工島。貿易が盛んだった地域)があり諸外国にもよく知られた港だったことや、その形が大型の船舶でも寄港しやすく、環境の良い港であったことがその理由です。現在でも、国際的交易港としてさまざまな国の船舶が停泊しています。
「長崎造船所」は長崎港にあり、ここは開国にあたって日本を守るために海軍が創設された場所です。オランダから海軍の教育のために教師団を招いて、造船技術を学ぶ際に使われた造船所でした。
ジャイアント・カンチレバークレーン
日本初の大型クレーンである「ジャイアント・カンチレバークレーン」は当時、最新の電動クレーンでした。イギリスのスコットランドで製造されたもので、150トンの荷物を吊り上げることができます。造船所でつくられたプロペラなどの大型の部品を船に積み込んだり、陸揚げする時に使用します。
第三船渠(せんきょ)
当時は東洋最大の西洋式船渠(ドック)として建造されました。1879年に第一船渠、1896年に第二船渠がつくられ、1905年に第三船渠がつくられました。多くの船が造船・修理されてきましたが、第一船渠は1963年に、第二船渠は1972年にそれぞれ閉鎖しました。これまでに三度の拡張工事を繰り返しましたが、明治時代につくられた船渠で現在も稼働しているのはこの第三船渠だけです。
これらは明治の産業革命で造船分野に大変活躍しました。そして、これらは歴史的な価値だけでなく現在も利用される稼働遺産としても有名です。どちらも、現在も造船に使われていることから一般公開はされていませんが、遠くから観察することは可能です。特にカンチレバークレーンは、その大型の姿から長崎の景観の一つとして楽しむことができます。
小菅修船場跡
小菅修船場は西洋の国から中古で仕入れた船や、外国からやってきた船舶が故障した時に、修理するためにつくられた修船場です。建造したのは、幕末期に活躍したイギリス人貿易商のトーマス・グラバー。今回の世界遺産登録で、旧邸宅が同じく世界遺産として認定されました。
この修船場は現在主流の船渠とは違い、日本で最初の蒸気機関を使った洋式ドックです。日本の近代造船の歴史でも最古の建造物とされ、造船所発祥の地と言われています。現在はその役目を終えていますが、当時「コンニャクレンガ」と呼ばれた引き上げ機があるレンガづくりの小屋など、独特な外観をとどめています。
三池港
福岡県にある三池港も今回の世界遺産を構成する一つです。この港は、三池炭鉱で生産される石炭を運び出すためにつくられたものです。潮の満ち引きの差が大きく、大型船の停泊が難しかった有明海に築かれた港として、当時は大切な役目を果たしました。この港は、有明海の特性を克服するためにいろいろな工夫が凝らされていることが評価されて世界遺産に登録されました。マサチューセッツ工科大学に留学して西洋技術を身につけた團琢磨(だん・たくま。実業家)がリーダーとなって完成させたため、日本では珍しい仕組みを数多く見ることができます。
たとえばハミングバード(はちどり)の形をした港や、有明海から流れ出る砂や泥をせき止めるための防砂堤、さらに水面の高さが違う状態でも船舶が入港できるようにつくられたパナマ運河式の閘門(こうもん)と呼ばれる船渠装置、船渠内の水を逃がして船舶を入港させるためのスルーゲートなどが挙げられます。
また、三池港も長崎造船所と同じく現在も稼働中の現役港です。團琢磨は、「この地に百年の基礎を」と考え築港したという逸話も残っており、当時の工夫や知恵が現代でも活かされている貴重な例としても価値があります。
明治維新の歴史は開国・造船の歴史
江戸時代の鎖国政策で250年もの間、海外との交流を断ち切って独自の発展を遂げてきた日本。明治維新にあたって、取り入れた西洋の技術や知識は当時の日本人にとっては、未知のものばかりであったに違いありません。それをわずか50年ほどで追いつき、さらに追い越そうとした躍進は、数多くの技術者や外国人指導者の存在があってこそのものです。その面影や活躍の様子を見ることができる遺跡は、まさに日本が誇る文化遺産と言えるでしょう。今回ご紹介したような造船を訪れると、当時の様子が垣間見られるはずです。ぜひ、足を運んでみてください。
制作:工場タイムズ編集部